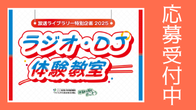テレビ番組
大河ドラマ 八重の桜〔50・終〕 いつの日も花は咲く
番組ID
211034
※放送ライブラリーの視聴ブースでは、番組IDを入力することで、簡単に番組を選べます。
※放送ライブラリーの視聴ブースでは、番組IDを入力することで、簡単に番組を選べます。
放送日時
2013年12月15日(日)20:00~20:59
時間(分)
59
ジャンル
swords
時代劇
recent_actors
ドラマ
放送局
NHK
製作者
NHK
制作社
NHK
出演者
綾瀬はるか、オダギリジョー、風吹ジュン、玉山鉄二、市川実日子、勝地涼、中村蒼、水原希子、加藤虎ノ介、太賀、香野百合子、荒井萌、貫地谷しほり、降谷建志、小泉孝太郎、長谷川博己、宮崎美子、尾花貴絵、近野成美、前野朋哉、談莫東、足立智充、鈴木梨央、田中明、豊田留妃、山岡愛姫、塩見大貴、渡辺早織、遠谷比芽子、堀田勝、出口哲也、ミョンジュ、峯村淳二、高橋智也、染川重樹、佐藤正浩、長棟嘉道、大竹浩一、小野孝弘、反町隆史、生瀬勝久、加藤雅也、村上弘明、西田敏行、語り:草笛光子、語り:久保田祐佳
スタッフ
作:山本むつみ、テーマ音楽:坂本龍一、音楽:中島ノブユキ、題字:赤松陽構造、タイトル画:菱川勢一、時代考証:本井康博、時代考証:山村竜也、考証:平井聖(建築)、考証:小泉清子(衣裳)、監修:伊藤佐智子(衣裳デザイン)、特殊メイク:江川悦子、指導:林邦史朗(殺陣)、指導:橘芳慧(所作)、指導:佐山二郎(砲術)、指導:酒井シヅ(医事)、指導:田中光法(馬術)、指導:望月暁云(書道)、指導:上野洋(裁縫)、指導:小澤宗誠(茶道)、VFXプロデューサー:結城崇史、ことば指導:新國弘子(会津)、ことば指導:井上裕季子(京)、ことば指導:中村章吾(薩摩)、ことば指導:一岡裕人(長州)、ことば指導:岡林桂子(土佐)、ことば指導:前田こうしん(熊本)、ことば指導:周来友(中国語)、制作統括:内藤愼介、プロデューサー:樋口俊一、美術:山田崇臣、技術:宮内清吾、音響効果:三谷直樹、撮影:大和谷豪、照明:高橋貴生、音声:中本一男、映像技術:木川豊、VFX:松永孝治、記録:塩井ヨシ子、編集:掛須秀一、美術進行:山本志恵、演出:加藤拓
概要
幕末、会津・鶴ヶ城での戦いにおいて最新のスペンサー銃を手に新政府軍に奮戦、「幕末のジャンヌ・ダルク」と呼ばれ、維新後はアメリカ帰りの新島襄の妻となり、共に同志社を設立した新島八重の生涯を描く。NHK大河ドラマ第52作。(2013年1月6日~12月15日放送、全50回)◆最終回「いつの日も花は咲く」。明治27年(1894年)、八重(綾瀬はるか)は、従軍篤志看護婦として広島陸軍予備病院で日清戦争の負傷兵たちを看護していた。院内は伝染病が発生して危険な状況だったが、八重はひるむことなく勇敢に看護に従事し、若い看護婦たちを見事に統率する。すると、その功績がたたえられ、皇族以外の女性で初となる宝冠章を叙勲。しかし、戦争がきっかけとなった叙勲を素直に喜べない八重は、晴れない気持ちを抱いたまま会津に帰郷するのだった。◆解説副音声あり