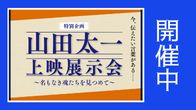テレビ番組
桜SOS ~フードバンクと令和の貧困~
番組ID
215785
※放送ライブラリーの視聴ブースでは、番組IDを入力することで、簡単に番組を選べます。
※放送ライブラリーの視聴ブースでは、番組IDを入力することで、簡単に番組を選べます。
放送日時
2020年05月06日(水)10:25~11:25
時間(分)
54
ジャンル
cinematic_blur
ドキュメンタリー
放送局
テレビ新潟放送網(TeNY)
製作者
テレビ新潟放送網(TeNY)
制作社
テレビ新潟放送網(TeNY)
出演者
スタッフ
概要
「子どもにおなかいっぱい食べさせてあげられない」とうい切ない思いを抱える母親が、この令和の時代にも多くいる。新潟県新発田市の民間団体「フードバンクしばた」は、経済的に厳しい家庭を支援するため、月に1~2回、米や食料品などを無償で届けている。番組では、支援を受けている家庭にアンケート調査を実施した。そこから浮かび上がってきたのは、現代社会では見えにくくなった貧困、声をあげられない人々のSOSだった。そして、進級や進学に掛かる費用に怯え、春の訪れに追いつめられている人々がいることがわかった。フードバンクの活動を通して、桜が咲き、本来なら希望にあふれるはずの“進学・進級の春”に苦しむ家庭の姿と令和の貧困の実態に迫る。