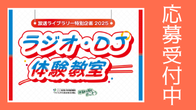テレビ番組
ハルとアオのお弁当箱〔1〕 カリカリ梅とゆかりのおにぎり
番組ID
216236
※放送ライブラリーの視聴ブースでは、番組IDを入力することで、簡単に番組を選べます。
※放送ライブラリーの視聴ブースでは、番組IDを入力することで、簡単に番組を選べます。
放送日時
2020年10月13日(火)00:00~00:30
時間(分)
24
ジャンル
recent_actors
ドラマ
放送局
BSテレビ東京(BSジャパン)
製作者
BSテレビ東京(BSジャパン)
制作社
BSテレビ東京(BSジャパン)、テレパック
出演者
スタッフ
原作:まちた、脚本:川崎いづみ、主題歌:H△G、撮影:佐藤勝成、照明:栗林映未里、VE:星野隼人、音声:蟻川真矢、技術プロデューサー:川田万里、技術デスク:星宏美、美術:宍戸美穂(装飾)、美術:庄島毅(統括)、スタイリスト:乙坂知子、スタイリスト:岩堀若菜、ヘアメイク:山本のぞみ、フード:はらゆうこ(コーディネーター)、フード:山崎千裕(コーディネーター)、イラスト:奥田悠樹、タイトル:林優希、編集:木谷瑞、編集:稲葉香(本)、MA:市村聡雄、選曲:谷口広紀、音響効果:荒川翔太郎、助監督:加治屋彰人、助監督:近藤信子、助監督:本間玉美、制作担当:高橋康進、制作担当:森田勝政、制作進行:金城一司、AP:佐藤瞳、AP:西村咲由梨、協力:里見陽子(レシピ)、編成:石本順也、HP:道本ミユキ、宣伝:安藤夏実、宣伝:加藤裕、コンテンツプロデュース:清水俊雄、コンテンツプロデュース:柳川美波、プロデューサー:戸石紀子、プロデューサー:園部雄一郎、プロデューサー:三本千晶、プロデューサー:吉川厚志、監督:東田陽介
概要
オタク女子とジェンダーレス男子がひょんなことから同居することに。同居のルールは「お互いのお弁当を作り合うこと」。心温まるお弁当を通した触れ合いによって、前向きに生きていく2人を描く。原作:まちた、脚本:川崎いづみ。(2020年10月13日~12月29日放送、全12回)◆第1回。大学図書館勤務のオタク女子・ハル(吉谷彩子)は、学生から「なんでいつも制服みたいな服なんですか?」「服もダメだし髪もダメですよ!」ときつい言葉を浴びせられる。ハルは、心の傷を手当するため行きつけのバーへ。そこで、ジェンダーレス男子のアオくん(井之脇海)と出会い、酔って意気投合し、勢いで同居を約束してしまう。しかし、翌日、ハルは「正気じゃなかった」と言い出す。そんなハルに手作りのお弁当を渡し去っていくアオ。お昼にアオのお弁当を食べたハルは、気持ちに変化が起こる。